村長ブログ(令和7年7月15日)
7月上旬は連日暑い日が続き、すっかり夏の気候となり山も賑わい始めています。




1日は、第6次総合計画策定に向けた計画審議会の初回が開催されました。
総合計画は、まちづくりの基本方針を定める極めて重要な計画として、各個別計画の最上位に位置付けられています。
白馬村では、現行の第5次総合計画の計画期間が令和7年度で終了することから、次の10年間を対象とする「第6次総合計画」を策定するため、昨年度から村民アンケートや各地区との懇談会等を行い、村民の皆様から意見をお聴きしてまいりました。今年度はそれらを基に基本構想や基本計画を立案し、村民の皆様に自分ごととして捉えていただける実効性のある計画を策定したいと考えております。
また、国では6月13日に「地方創生2.0基本構想」が閣議決定されました。これまでの10年間の地方創生の成果と反省が整理されるとともに、次の10年間に向けて、人口減少を正面から受け止めた上で、多様な関係者と議論して総合戦略を策定することが重要であると示されています。白馬村の総合計画は、地方版総合戦略を含むものとして策定しますので、国や県の動向も踏まえながら内容を検討していくこととなりますが、この計画審議会は、まさに様々な分野を代表する皆様に委員に就任いただいております。
なお、今回の計画策定に併せて、白馬村では「自治基本条例 (仮称)」を制定したいと考えております。自治基本条例は、まちづくりに関する基本的な ルールや村民・議会・行政等の役割を定め、様々な条例の最上位に位置付けられる市町村の憲法のようなものです。
外的な要因の影響を受けやすく、人の出入りも多い白馬村において、時代を越えて大切にするべきものは何なのか、皆さんと一緒に考えて、共通の認識を持ちながらより良い未来に進んでいきたいと考えております。
皆様のご協力とご支援により、さらに美しく魅力的で住みやすい白馬村に向けて地域一丸となる計画を策定できるようお願い申し上げます。
7月30日には、白馬村の将来像について、村民一人ひとりの想いを形にするために、まちづくり村民ワークショップを開催します。
ぜひ皆様ご参加ください。


同日は、平和大行進に参加された皆様に激励の言葉を述べさせていただきました。
戦後80年を迎え、実際に戦争を体験した方たちも徐々に少なくなっていく中、私たちは二度と戦争の惨禍を繰り返すことのないよう、平和を尊び、次代へと記憶と想いを繋いでいかなくてはなりません。
世界に目を向けますと、ウクライナや中東では争いが起きていて、罪のない人たちが生活や命を奪われる悲惨な状況が今なお続いており、ニュース等でその惨状を目にするたびに、胸が締め付けられる思いがします。
戦争を知らない私たちは、これまで以上に当たり前の日常に感謝し、命の大切さ、心の平和の尊さを語り継ぎ、子どもたちと共に育んでいく責任があると感じます。
白馬村の自然と人とのつながりを守りながら、確かな平和への願いを発信し続けていきたいと思います。

3日は、「第75回社会を明るくする運動」が開催されました。
「社会を明るくする運動」は犯罪や非行の防止、そして罪を犯した人の更生について理解を深め、地域全体で支え合い、誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指す全国的な運動です。
75回という長きにわたり、地域の皆様と共にこの活動を継続できておりますことに、改めて敬意を表し感謝申し上げます。
また、日頃より更生保護活動や雇用支援などにご尽力をいただいております保護司や更生保護女性会の皆様、協力企業の皆様に重ねて御礼申し上げます。
今回は、各地で更生保護活動に携わって来られた松川村の保護司の錦織さんを講師に招き、これまでのご経験をもとに、当事者との向き合い方について、講演いただきました。
ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。


5日は、長野県白馬高等学校の「しろうま祭」に伺いました。
この日は、午前中に白馬高校の学校運営協議会があり、卒業生の方から、現在の活躍と白馬高校時代のエピソード、現在に生かされていることなどが報告され、非常にポジティブなものが多かったので大変嬉しく感じ、その後に拝見した文化祭でしたので、より特別な思いで楽しませていただきました。
例年に比べ多くの方が訪れており、私も短い時間でしたがステージや教室のイベントが大変盛り上がっている様子や生き生きとした生徒の顔を拝見することができ、非常に嬉しく思いました。


同日は、「全麺協中日本支部そば打ち技術研修会・講習会」が開かれ、開会のご挨拶に伺いました。
昨年も白馬村で開催いただきましたが、今年もこのイベントが当村で開催され多くの方にお越しいただけましたことを大変嬉しく思います。
長野県は日本有数の蕎麦の産地であり、白馬村もその環境を受け継いできました。白馬の清らかな水と冷涼な気候が、蕎麦の栽培に適しているため、古くから蕎麦が作られてきており、白馬村には20ほどの蕎麦処があり、地元産のそば粉を使った手打ち蕎麦を堪能することができます。
日本の食文化の中でも、蕎麦は深い歴史と伝統を持つ特別な存在ですが、その蕎麦打ちの技術をさらに磨き、高みを目指すために集われた皆様に心から敬意を表します。
貴重な認定・講習会の機会を存分に活かし、蕎麦打ちの奥深さをさらに探求し、技術と知識が磨かれたことと存じます。
今回参加者の方々が打ったお蕎麦は、昨年同様に、白馬村内の福祉施設をはじめ、白馬村の皆様に2000食以上を無料提供いただきました。食品を無駄なく活かす、SDGsの観点からも大変晴らしい取組であり、改めて感謝申し上げます。


7日は、役場職員で、村内施設や道路脇の草刈りや草むしりを実施し、通常業務後の作業でしたが、職員の皆さんに暑い中頑張っていただきました。
私はオリンピック道路脇を担当しましたが、ポイ捨てゴミも比較的多くあり、お越しになる皆様におかれましては、くれぐれもゴミのポイ捨て等しませんようお願いいたします。
また、現在【夏の村民草刈りWeek】が始まっております。
本格的な夏シーズンを前に、気持ちよくお客様をお迎えできるように、また農地の保全や熊をはじめとした有害鳥獣被害対策のため、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
お越しになる皆様におかれては、美しい白馬村の景観維持へのご理解、ご協力をお願いします。


11日は、【平成7年7月11日豪雨災害から30年シンポジウム】が小谷村で開催されました。
今から30年前、同日は白馬村でもかつてないほどの豪雨となり、少なからず被害がありましたが、姫川下流にあたるお隣の小谷村で広範囲に渡る大きな災害が発生しました。
今回のシンポジウムでは、実際に当時避難された方や避難所運営、復興に当たられた方、当時の消防団長等が登壇し、小谷中学生が質問する形でデスカッションが行われ、当時の大変な様子や、災害時に必要なことが何であるかといった事が、会場の皆さんや子ども達に伝えられました。
地元小学生や中学生による災害への備えの発表もあり、大変有意義なシンポジウムとなりました。
皆様におかれましては、ハザードマップや避難所の確認、日ごろからの備えをくれぐれもお願い申し上げますとともに、災害発生の畏れがある際の早めの避難と、自助・共助・近助へのご協力をよろしくお願いします。
村民の安全を守るため、昼夜を分かたず努力してくださっております白馬村消防団や役場職員、消防署、警察署、インフラ整備事業に携わっていただいております皆様はじめ、地域役員等をお務めいただいております皆様に、改めまして深く感謝申し上げます。


13日は、第12回目となる【ジャパンEVラリー白馬2025】が開催され、表彰式プレゼンターとして参加しました。
主催者並びに関係者の皆様の長年に渡る熱心で継続的な取組に対しまして、心より敬意を表しますとともに、観光地の地球環境対策を意識した取組を毎年白馬村で開催していただいていることに対し、厚く御礼申し上げます。
白馬村は、地球環境にやさしい持続性あるリゾートを目指しており、日本EVクラブ並びに白馬EVクラブの取組に賛同し、引き続きEV推進やシェアリング事業に協力してまいりたいと考えております。
白馬村では、2030年に向けたアクションプラン「ゼロカーボンロードマップ」を作成し、温室効果ガス削減と生物多様性の回復に向け、取り組んでおります。
皆様も可能なアクションや行動変容にご協力をいただけますと幸いです。
EVラリーにご参加いただきました皆様ありがとうございました。

この夏も、多くのお客様に、白馬村の美しい自然や魅力的なアクティビティーをご堪能いただき、滞在をご満喫いただければと思います。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら
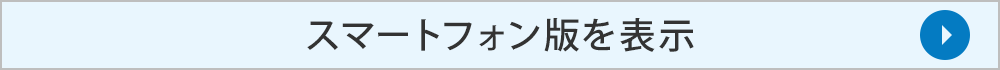







更新日:2025年07月15日