非農地証明について
概要
農地を転用し、これを登記しようとする場合には、農地法第4条又は5条の許可が必要となります。
登記簿上の地目が農地である土地が何等かの事由により非農地化したもののうち、農地法上の転用許可制度を適用しないことが適当と認められるものについてのみ当該証明書を発行することにより、農地制度の適正な運用を図るものです。
なお、非農地証明は農地法などの法律に基づく業務ではなく、登記手続の便宜を図るために、農業委員会が実施しているサービス業務です。
交付条件
- 農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から注1)非農地であった土地
- 自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
- 耕作不適、耕作不便でやむを得ない事情によって、注2)原則20年程度耕作放棄されたため自然潰廃した土地で、注3)復元が困難な土地
- 人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に20年以上経過し、注4)復元が困難であり、注5)農地行政上、特に支障がないと認められる土地
- 一般の交通の用に供する注6)舗装された道路になってから既に10年以上経過している土地
- 農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域内の土地でないこと
- 農地法第51条(違反転用に対する処分)の対象となった土地でないこと
- 利用権等が設定された土地でないこと
(注1)非農地であった土地とは、農業以外の目的に利用されていた土地で現況もその状態が続いているものをいいます。
(注2)原則20年程度とは、(注3)復元が困難な場合に規定する条件程度に荒廃・雑木が成長するおおよその期間を表すものであって、土地利用や周辺環境によって前後する可能性があり、一概に判断されるものではありません。
(注3)復元が困難とは、森林、湖沼の様相を呈しており、人力又は農業用機械では耕起、整備ができない土地など、農地に復元するための物理的な条件が著しく困難な場合をいい、除草、耕耘機やトラクター等を入れれば農地に復元できるものについては証明できません。
(注4)復元が困難とは、土地の大部分に建物が建設されている、コンクリート等で全面舗装されているなど容易に農地に戻せない状態をいいます。地面が土・砂利等のもの、地面が土のまま資材置場・駐車場等に使われているもの、土地の一部分のみがコンクリート舗装等のものについては証明できません。普及困難な部分で分筆後に証明申請してください。
(注5)農地行政上、特に支障がないとは、隣接農地に対しての被害防除等に問題がないこと、他関係法令に基づく指導等を受けていないことをいいます。
(注6)舗装された道路とは、コンクリート等で全面舗装されたものをいい、地面が土・砂利等のもの、土地の一部分のみが舗装されたものについては証明できません。舗装された道路部分で分筆後に証明申請してください。
提出書類
- 農地法第2条の農地でない旨の証明願(様式1号)
- 該当地の土地登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
- 住民票又は戸籍の附票の写し(現住所と土地登記事項証明に記載された住所が異なる場合)
- 附近見取図及び公図
- 始末書(交付条件の4、5の場合)
- 現況写真(3方向以上からの撮影)
- 農地法第2条の農地に該当しない旨の注)客観的証明資料 6で確認できる場合は省略可
- 非農地証明に関する意見書・現地確認書(様式2号)
- その他農業委員会が必要と認めた書類
注)客観的証明資料について
交付条件1~5に該当することを客観的に証明できる資料(過去の状況や経緯が分かるもの)を添付してください。
証明資料の例
- 公的機関が発行した航空写真(撮影日が記載されたもの)(国土地理院撮影の航空写真財団法人日本地図センター発行もの)(村税務課発行の航空写真)等
- 建物がある場合は、建物登記事項証明書(閉鎖登記簿)
- 固定資産税課税明細書
- 自然災害前の写真、自然災害時の新聞の記事等
農業委員等の現地確認・意見について
農業委員若しくは農地利用最適化推進委員の2名以上で現地確認を行う必要があります。
ただし、農業委員又は農業委員会事務局長が必要と認めたときは、他の農業委員、農地利用最適化推進委員、自治会長、隣接地の所有者等、地域に精通した他の者の意見書等の追加資料を提出や現地調査及び事情聴取を行う場合もあります。
要綱・様式
非農地証明の交付基準について (Wordファイル: 28.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
みなさまのご意見をお聞かせください。
このページに関するご意見は、お問合せフォームをご利用ください。
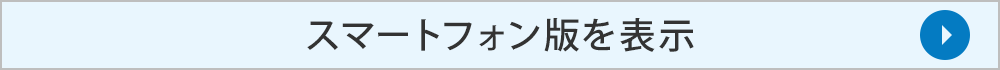







更新日:2020年07月01日