いわゆる「年収の壁」に関する令和7年度税制改正の主な内容について
「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」として、所得税(国税)及び住民税(村県民税)の制度が改正されました。
改正後の制度は、令和7年中(令和7年1月1日~12月31日)の収入について、令和7年度分所得税及び令和8年度分住民税から適用となります。
所得税に関する税制改正については、詳しくは国税庁のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
その他、年収の壁に関わらない住民税の改正点については、令和8年度からの個人住民税の主な改正点(内部リンク)もご確認ください。
給与所得者について、非課税となる収入の上限が変わります。
- 所得税の基礎控除額が、48万円から最大95万円まで引き上げられました。
- 所得税と住民税の給与所得控除の最低保障金額が55万円から65万円に引き上げられました。


住民税について、ご注意ください
住民税は「地域社会の会費」という性格上、所得税とは控除の仕組みが異なります。そのため、年収103万円を超えると課税されます。
実質的な手取り金額への影響については、税負担以外に発生する社会保険料の負担や、各種給付・手当等の変化なども別途考慮する必要があります。
給付・手当・サービス等の中には、住民税が非課税であることが要件となるものや、収入金額によって内容が変動するものがあります。
控除の対象となる大学生年代の子等に係る収入要件が変わります。
アルバイト等により収入を得ている大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等について、
- 扶養控除(特定扶養親族)が適用される合計所得金額の上限が、58万円(給与収入に換算すると123万円)に引き上げられました。(現行:48万円、給与収入に換算すると103万円)
- 上記1の上限を越えた場合でも、合計所得金額123万円(給与収入に換算すると188万円)までは親等が控除を受けられる新たな仕組みが導入されました(控除額は段階的に減少)


控除の対象となる配偶者の収入要件が変わります。
パート等により給与収入を得ている配偶者について、
- 配偶者控除が適用される合計所得金額の上限が、58万円(給与収入に換算すると123万円)に引き上げられました。(現行48万円、給与収入に換算すると103万円)
- 給与所得控除の最低保障金額が65万円(現行:55万円)に引き上げられたことにより、配偶者特別控除の適用時、配偶者と同額の控除が受けられる給与収入の上限が160万円となりました(現行:150万円)


参考:個人住民税と所得税の主な改正事項

参考:年収の壁比較表 年間給与収入に応じた各種制度(令和7年度税制改正による変化)

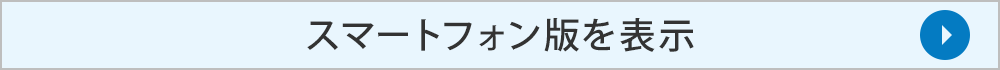







更新日:2025年09月29日